ここから本文です
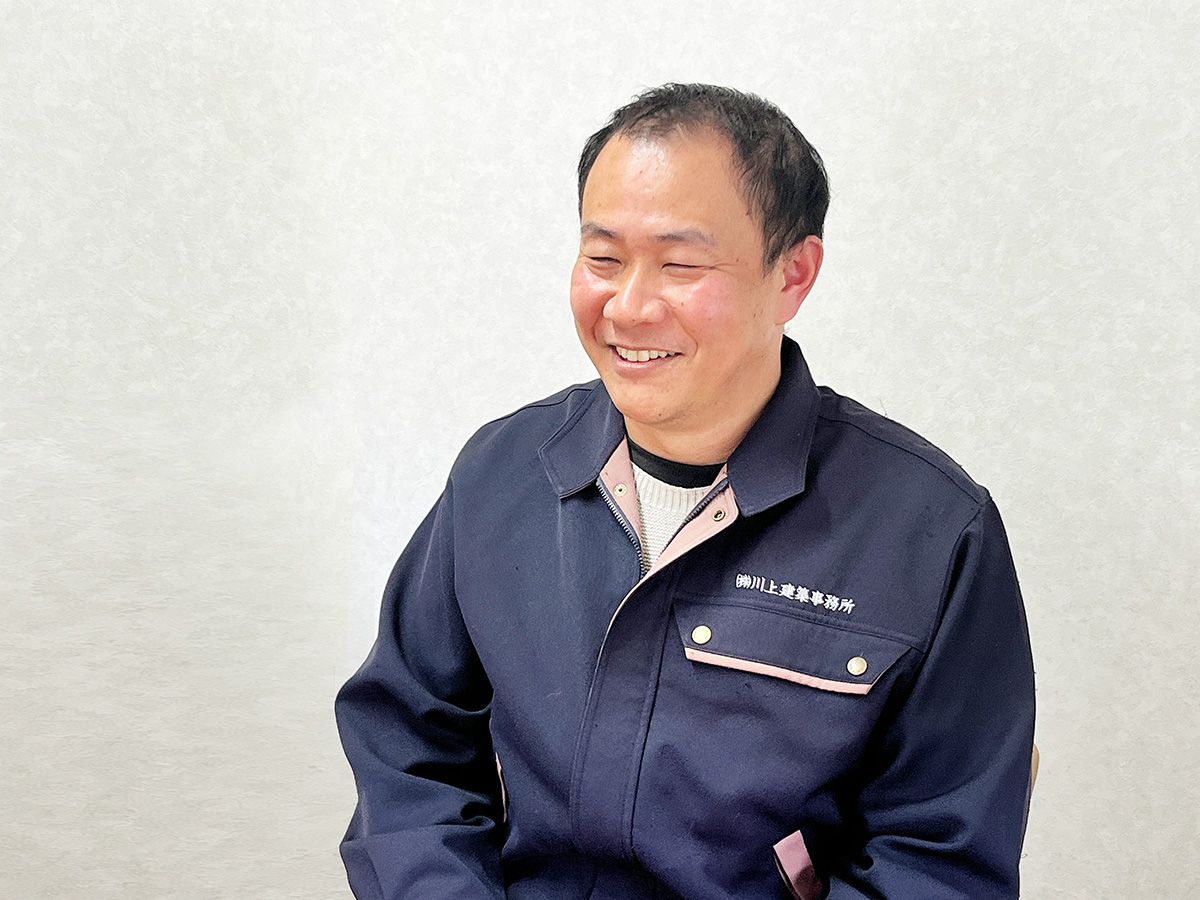
好きな空間を
実現できる建築は、
他には替え難いほど
魅力ある世界
Profile
名古屋工業大学工学部卒。42歳。大学卒業後は岐阜市内の建築事務所に入社し、構造設計を専門とする建築士として経験を積む。3年後、実家の家業である川上建築事務所に転職。父、母、姉ともに建築士という建築一家で、地域に根ざした活動で定評がある。
KAWAKAMI
株式会社川上建築事務所
一級建築士
川上さん
※取材・撮影:2025年2月
得意分野を活かして構造設計の道へ
建築士を目指したきっかけを教えてください
 やはり家業でもあり、特に我が家では母も二級建築士で、子育てをしながら図面を引くという姿を見て育ったので、自然な成り行きだったのかなと思います。跡を継ぐということに対してもあまり反発するとかはなくて、中学生くらいの時にはもう「建築士になるんだ」っていう感じにはなってましたね。この建築事務所は父が昭和61年に立ち上げた会社ですが、今は父が会長、私が社長を務めています。外部に対して代表として対応する一方で、構造設計の業務についても私が担当しています。
やはり家業でもあり、特に我が家では母も二級建築士で、子育てをしながら図面を引くという姿を見て育ったので、自然な成り行きだったのかなと思います。跡を継ぐということに対してもあまり反発するとかはなくて、中学生くらいの時にはもう「建築士になるんだ」っていう感じにはなってましたね。この建築事務所は父が昭和61年に立ち上げた会社ですが、今は父が会長、私が社長を務めています。外部に対して代表として対応する一方で、構造設計の業務についても私が担当しています。
どのようにして構造設計に携わるようになったのですか?
 大学で専攻を決めていくにあたって、自分自身「力学」が得意だったということもあって「構造」を専門にやってみようと思いました。また、クラスに阪神・淡路大震災で被災したという友人がいて色々と当時の話を聞いたのですが、やはり建物の倒壊などで身近な方が亡くなったということもあったそうです。そうした時に大学の授業で「家というものは住む人が絶対に安心できる場所であるということを実現しなければならない」ということを仰っていた先生がいて、今も特に印象深く覚えています。当時も構造を専攻で選ぶ学生は少ない状況で、「だったら自分がやろう」という気持ちになりました。
大学で専攻を決めていくにあたって、自分自身「力学」が得意だったということもあって「構造」を専門にやってみようと思いました。また、クラスに阪神・淡路大震災で被災したという友人がいて色々と当時の話を聞いたのですが、やはり建物の倒壊などで身近な方が亡くなったということもあったそうです。そうした時に大学の授業で「家というものは住む人が絶対に安心できる場所であるということを実現しなければならない」ということを仰っていた先生がいて、今も特に印象深く覚えています。当時も構造を専攻で選ぶ学生は少ない状況で、「だったら自分がやろう」という気持ちになりました。
卒業後の進路の決め方はどのようなものでしたか?
 構造を専攻して学んだものの、当時家業の事務所ではその分野の専門家はいなかったため、実務としての経験が豊富な別の事務所に就職しました。かなりの激務でしたが、大変勉強になりました。また当然ですが実際に建物になっていく過程を体験するので、学生時代はその部材だったりとか、平面でしか考えていなかったなと実感しましたね。そのため先輩からは「作りやすいように設計しろ」ということも教えてもらいました。
構造を専攻して学んだものの、当時家業の事務所ではその分野の専門家はいなかったため、実務としての経験が豊富な別の事務所に就職しました。かなりの激務でしたが、大変勉強になりました。また当然ですが実際に建物になっていく過程を体験するので、学生時代はその部材だったりとか、平面でしか考えていなかったなと実感しましたね。そのため先輩からは「作りやすいように設計しろ」ということも教えてもらいました。
また当時は、一級建築士の資格が卒業後2年間の実務経験が必要となっていたため、仕事をしながら勉強はずっと続けていました。今はだいぶ楽になったのではと思います。
地域の事業で知った「再生させる」という喜び
建築士の魅力はどんな点ですか?
 新しい建物を建てるというのはもちろんですが、実は最近、関市からの依頼で行った業務で「古民家を地域の公共施設として再生させる」というものがありました。全国的に「空き家問題」が取り沙汰されていますが、古い建物でも構造上活かせる梁や柱はそのままにして、あとは用途に応じて使いやすく結構好き勝手に間取りなどを変えることができるんですね。それも建築という仕事の醍醐味の一つではないかと感じています。
新しい建物を建てるというのはもちろんですが、実は最近、関市からの依頼で行った業務で「古民家を地域の公共施設として再生させる」というものがありました。全国的に「空き家問題」が取り沙汰されていますが、古い建物でも構造上活かせる梁や柱はそのままにして、あとは用途に応じて使いやすく結構好き勝手に間取りなどを変えることができるんですね。それも建築という仕事の醍醐味の一つではないかと感じています。
この建物は「古民家あいせき」という名前で、子どもたちが学校が終わった後にここで勉強したりとか、本当に皆さんに喜ばれていて、「地域の自慢や」なんて話されているのを聞くとすごく鼻が高いです。これからはこうした分野でも貢献していけたらと思っています。
これから建築業界についてどのようにお考えですか?
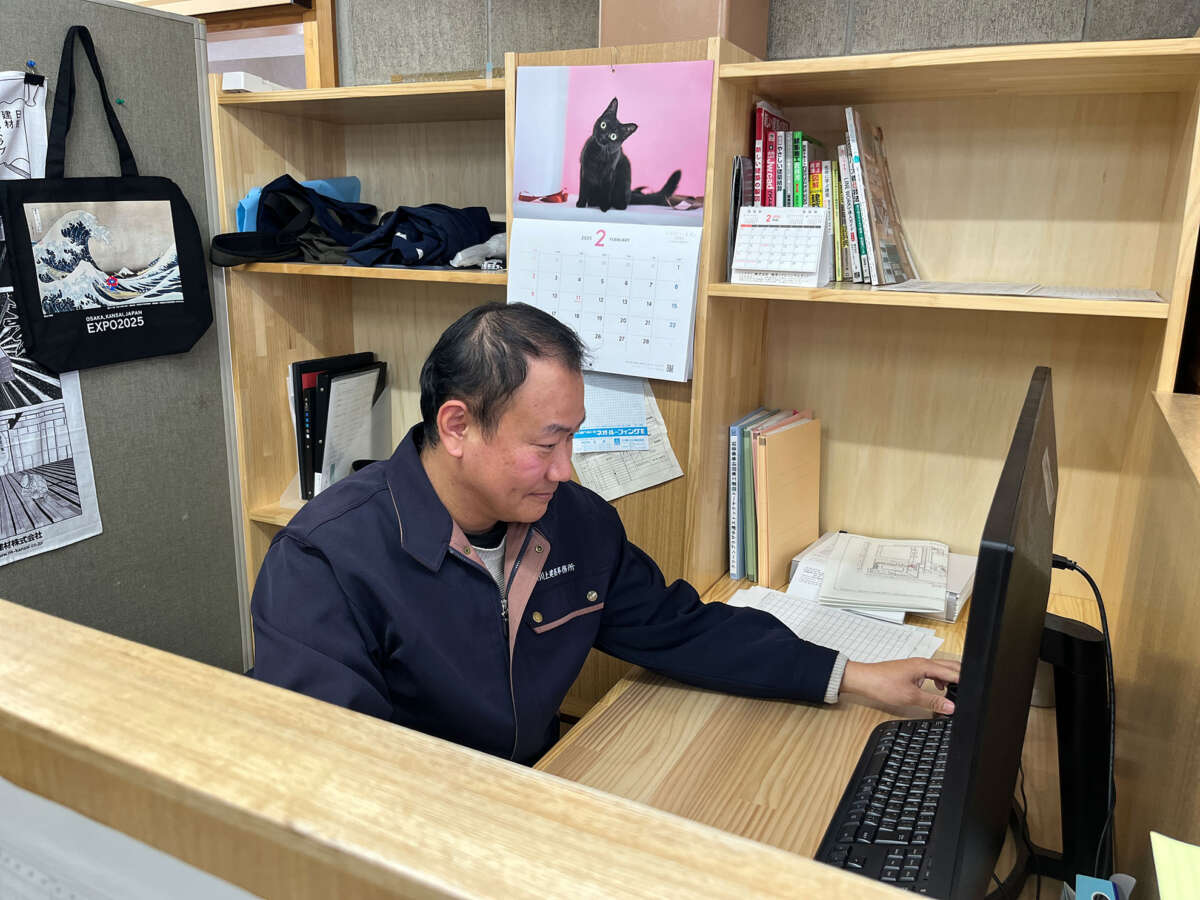 構造の専門家だからということもありますが、街を歩いていると「この建物ちょっと危ないんじゃないかな」と思ってしまうことがあります。今も構造の建築士のなり手は少ないのですが、建物の安全を確保する上で大切な仕事なので、どんどん目指していってほしいですね。構造の仕事はどれだけAIが進んだとしても、チェックする人間が必要なので絶対になくなりはしないと思っています。
構造の専門家だからということもありますが、街を歩いていると「この建物ちょっと危ないんじゃないかな」と思ってしまうことがあります。今も構造の建築士のなり手は少ないのですが、建物の安全を確保する上で大切な仕事なので、どんどん目指していってほしいですね。構造の仕事はどれだけAIが進んだとしても、チェックする人間が必要なので絶対になくなりはしないと思っています。
あと「大工さんになりたい」という高校生も結構いるものの、すぐに辞めてしまうこともあると聞いています。でも「空間を作り上げる、実現する」というのは建築の仕事ならではだと思うので、そうしたところにやりがいを感じて一緒に頑張っていけたらいいですね。
INTERVIEW先輩インタビュー
-

OKUDA
株式会社吉川組
建築施工管理奥田さん
-

KAWAKAMI
株式会社川上建築事務所
一級建築士
川上さん
-

AKIHIRO
ANDO
安藤 昌寛さん
-

TOMOYO
NONODA
有限会社荒井建築設計事務所
一級建築士
建築積算士
測量士補野々田 知代さん
-

YASUHIRO
FUJITO
1級電気施工管理技士
第一種電気工事士藤戸 康弘さん
-

MEGUMI
FUJII
(株)ウカイ設計
一級建築士藤井 恵さん
-

KAZUKI
NAITOU
株式会社 向井建築事務所
設計・建築内藤 和揮さん
-

KAZUHIRO
TAKEUCHI
(株)廣建築設備設計
設計・設備竹内 一廣さん
-

KAZUYA
OGAWA
内藤建設 株式会社
施工・建築小川 和哉さん

